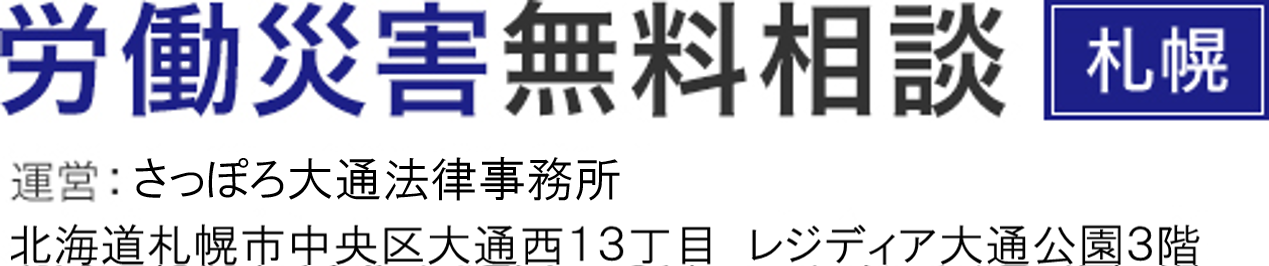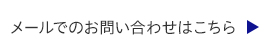下肢の後遺障害
1 欠損障害
欠損障害とは、事故により直接に身体の一部が切断されてしまったり、壊死が生じて治療として切断を強いられる場合であり、その欠損の程度により等級が認定されます。
|
等 級 |
障害の程度 |
|
1級の8 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
|
2級の4 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
|
4級の5 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
|
4級の7 |
両足をリスフラン関節(足根骨と中足骨との間の関節)以上で失ったもの |
|
5級の3 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
|
7級の8 |
1下肢をリスフラン関節(足根骨と中足骨との間の関節)以上で失ったもの |
2 機能障害
機能障害とは、3大関節の動きの障害であり、その可動域の制限の程度により等級が認定されます。
したがいまして、機能障害においては、適切な時期に正確な可動域の測定を受けることが重要です。
関節可動域の測定には、①被害者が自発的に曲げる自動運動を測定するものと、②医師が手を添えて曲げる他動運動を測定するものがありますが、後遺障害の認定には、原則として他動運動を測定したものが採用されます。
ただし、神経の麻痺を原因とした機能障害の場合、そもそも自発的に曲げる自動運動が不能であるにも関わらず、他動運動の測定では正常な可動域となってしまいます。したがいまして、後遺障害の診断書に「麻痺を原因とするため自動運動が不能である」旨の記載をしてもらう必要があります。
また、機能障害は受傷していない側の下肢との比較で、後遺障害を認定するのですが、受傷していない側の下肢がそもそも事故前から機能障害を負っている場合があります。この場合には、比較しても意味がありませんので、後遺障害の診断書に「健側の関節に、事故前からの可動域制限が存在するため、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会の定める参考可動域角度との比較をする必要がある」旨の記載をしてもらう必要があります。
測定は医師が行うのですが、必ずしも可動域の測定に精通していない医師も少なくなく、被害者の疼痛を全く無視して無理やり押し曲げて他動運動を測定する医師もいらっしゃるようです。機能障害は、障害が残ってしまった関節の可動域が、健康な側の可動域の2分の1ないし4分の1に該当するか否かで、機械的に判定が下されますので、わずか5度の測定の違いで、数百万円以上、受領できる賠償金等が異なることも少なくありません。
正確な測定を受ける必要性が高いことに注意が必要です。
被害者の方は、総じて、治療をできるだけ長く受けることを希望されることが多いのですが、後遺障害認定との関係では必ずしも、長く治療を受ければプラスに働くとは言い切れません。適切な時期に症状固定の診断を受けることが必要になる場合もあります。骨折等における症状固定(治療を受けてもこれ以上症状の改善が望めない状態)の時期については、注意が必要です。
|
等 級 |
障害の程度 |
|
1級の9 |
両下肢の用を全廃したもの |
|
5級の5 |
1下肢の用を全廃したもの 「下肢の用を廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節、足関節)のすべてが強直したもの(3大関節に加えて足指全部が強直したものも含まれる) |
|
6級の6 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
|
8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 「関節の用を廃したもの」とは、①関節が強直したもの、②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの、③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの |
|
8級に準ずる |
1下肢の3大関節の全ての関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
10級の10 |
1下肢の3大関節中の1関節に著しい障害を残すもの 「関節に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの、②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの |
|
10級に準ずる |
1下肢の3大関節の全ての関節の機能に障害を残すもの |
|
12級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節に障害を残すもの 「関節に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの |
3 動揺関節
動揺関節とは、靭帯損傷等により関節の安定性が損なわれてしまい、関節が正常より大きく可動するようになった場合や異常な方向に動くようになった場合をいいます。
動揺の程度について、ストレスXP撮影を行うことにより証明可能です。
|
等 級 |
障害の程度 |
|
8級に準ずる |
常に硬性補装具を必要とするもの |
|
10級に準ずる |
時々硬性補装具を必要とするもの |
|
12級に準ずる |
重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |
4 習慣性脱臼及び弾発ひざ
|
等 級 |
障害の程度 |
|
12級に準ずる |
習慣性脱臼及び弾発ひざ(ひざ関節の屈伸運動の際、一定の角度で抵抗があり、その角度を通過すると急にばね状に屈伸できるようになる状態) |
5 変形障害
変形障害は、通常レントゲン等により明確になるため、後遺障害認定において問題になることは少ないと考えられます。
しかしながら、医師によっては、いわゆる偽関節(骨折部の骨癒合が止まってしまい、異常な可動を示す状態)等について、治療の限界を認めることになるためか、後遺障害の診断書に明確に記載しないことがあります。そのような場合は、事故による不可避的なものであることを医師と十分に話し合って、後遺障害の診断書に明確に記載してもらうことが重要です。
|
等 級 |
障害の程度 |
|
7級の10 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ①常に硬性補装具を必要とするもので、大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ②常に硬性補装具を必要とするもので、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ③常に硬性補装具を必要とするもので、脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの |
|
8級の9 |
1下肢に偽関節を残すもの ①大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ③脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの |
|
12級の8 |
長管骨に変形を残すもの ①大腿骨に15度以上の変形を残すもの ②脛骨に15度以上の変形を残すもの ③腓骨に著しい変形を残すもの ④大腿骨又は脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの ⑤腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの ⑥大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの ⑦大腿骨又は脛骨の直径が3分の2以下に減少したもの ⑧大腿骨が外旋45度又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの |
6 短縮障害
下肢の短縮については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって、測定します。
骨折等により、一方の下肢の長さが短くなってしまうことは珍しいことではありません。
以下のとおり、短縮の幅が1センチ、3センチ、5センチで、それぞれ大きく等級が異なります。
短縮が、0.8センチであれば、後遺障害は認定されないのですが、1センチであれば、13級に認定されます。非該当と13級では、賠償金に数百万円の違いが生じるのが通常です。極めて慎重に測定してもらう必要があることが理解できるかと思います。
医師によっては、正確な測定箇所を把握していないケースもあり得ますので、注意が必要です。
|
等 級 |
障害の程度 |
|
8級の5 |
1下肢を5cm以上短縮したもの |
|
10級の7 |
1下肢を3cm以上短縮したもの |
|
13級の8 |
1下肢を1cm以上短縮したもの |
7 足指の障害
①欠損障害
|
等 級 |
障害の程度 |
|
5級の6 |
両足の足指の全部を失ったもの |
|
8級の10 |
1足の足指の全部を失ったもの |
|
9級の10 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
|
10級の8 |
1足の第1の足指を失ったもの 1足の他の4の足指を失ったもの |
|
11級に準ずる |
1足の第2の足指を含み3の足指を失ったもの |
|
12級の10 |
1足の第2の足指を失ったもの 1足の第2の足指を含み2の足指を失ったもの 1足の第3・4・5の3の足指を失ったもの |
|
13級の9 |
1足の第3・4・5の足指の1又は2の足指を失ったもの |
「足指を失ったもの」とは、足指を中足指節関節から失ったものをいいます。
②機能障害
|
等 級 |
障害の程度 |
|
7級の11 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
|
9級の11 |
1足の足指を全部の用を廃したもの |
|
11級の8 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
|
12級の11 |
1足の第1の足指の用を廃したもの 1足の他の4の足指の用を廃したもの |
|
13級に準ずる |
1足の第2の足指を含み3の足指の用を廃したもの |
|
13級の10 |
1足の第2の足指の用を廃したもの 1足の第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの 1足の第3・4・5の3の足指の用を廃したもの |
|
14級の8 |
1足の第3・4・5の足指の1又は2の足指の用を廃したもの |
「足指の用を廃したもの」とは、以下のいずれかの場合が該当します。
・第1の足指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
・第1の足指以外の足指を中節骨若しくは基節骨で切断したもの、遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
・中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の2分の1以下に制限されるもの
「用廃」とはいいますが、その語感とは異なり、実際には、骨の一部を失った場合が該当することに注意が必要です。